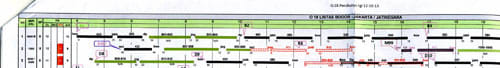本日、6月30日から埼京線では新型車両のE233系が運行されましたが、来年1月頃までには全ての205系がE233系に置き換わり、その後においても横浜線に順次E233系が導入されることから、205系の動向が注目されています。今後、これらの500両以上にもなる205系が地方へ転出となるのか、他の鉄道会社へ譲渡されるのか、それとも廃車になってしまうのか公式的な発表はいっさいありませんが、地方へ転出するにしても500両にもおよぶ車両数は必要でないと推測されますし、ジャカルタの現地メディアの報道では情報の内容にバラツキがあるものの、今年(来年分も含めて?)は180両、その後においては2018年までに毎年約160両を日本から中古車両を投入するということが報道されていますので、ジャカルタ(KCJ)に導入されるとしたらこの205系が最有力ではないかと個人的に推測しております。
205系のKCJへの譲渡が実現されるのかどうかわかりませんが、少々時間がありましたので、簡単ながらジャカルタ塗装を考えてみました。
現在、KCJ所有の車両については赤と黄色が採用され、PT.KAIの車両については青と黄色が採用されていますので、下のようにそれらの色を踏襲してみました。
![]()
前面全体を現在採用しているKCJカラーで覆ってしまうとメトロの6000系や7000系のようにあまりにも度派手になってしまいますので、帯部分に色を付けるほうがシンプルで良いのではないかと思っていますが、インドネシア人にとっては日本人には考えられないセンスがありますので、インドネシア人のセンスを考慮しながら他にいくつかのデザインも考えてみたいと思っております。
また、ジャカルタの103系ですが一昨年の夏から2代目青系塗装から東海色へと変更されましたが、またまた検査時期も近づきつつあるということで、いくつかのデザインを考えてみました。
私自身のオリジナルデザインはありませんが、左から115系にも採用されている長野色、私の地元を走る神奈中色、播但線でおなじみのワインレッド、PT.KAIの標準色です。次回検査時期に関して詳しいことはわかりませんが、検査時期が迫っているようでしたら早急に他のパターンも作成し、PT.KAIにいくつかのデザインを提出して、前回の東海色と同様に採用されることを願っております。
![]()
最後に、つい先日の現地の新聞発表によりますと2014年からKCJ管内のコミューターは10両化が実施されるとのことです。
205系が譲渡された場合においては、埼京線10両編成は問題ないかと思われますが、横浜線は8両編成ですので、足りない2両をどのように解決するのか、6扉車の動向なども気になるところです。
また、皆様にお願いですが、この記事については私の推測のもとで書いたことですので、この件に関して関係する鉄道事業社への問い合わせはご遠慮ください。
205系のKCJへの譲渡が実現されるのかどうかわかりませんが、少々時間がありましたので、簡単ながらジャカルタ塗装を考えてみました。
現在、KCJ所有の車両については赤と黄色が採用され、PT.KAIの車両については青と黄色が採用されていますので、下のようにそれらの色を踏襲してみました。

前面全体を現在採用しているKCJカラーで覆ってしまうとメトロの6000系や7000系のようにあまりにも度派手になってしまいますので、帯部分に色を付けるほうがシンプルで良いのではないかと思っていますが、インドネシア人にとっては日本人には考えられないセンスがありますので、インドネシア人のセンスを考慮しながら他にいくつかのデザインも考えてみたいと思っております。
また、ジャカルタの103系ですが一昨年の夏から2代目青系塗装から東海色へと変更されましたが、またまた検査時期も近づきつつあるということで、いくつかのデザインを考えてみました。
私自身のオリジナルデザインはありませんが、左から115系にも採用されている長野色、私の地元を走る神奈中色、播但線でおなじみのワインレッド、PT.KAIの標準色です。次回検査時期に関して詳しいことはわかりませんが、検査時期が迫っているようでしたら早急に他のパターンも作成し、PT.KAIにいくつかのデザインを提出して、前回の東海色と同様に採用されることを願っております。

最後に、つい先日の現地の新聞発表によりますと2014年からKCJ管内のコミューターは10両化が実施されるとのことです。
205系が譲渡された場合においては、埼京線10両編成は問題ないかと思われますが、横浜線は8両編成ですので、足りない2両をどのように解決するのか、6扉車の動向なども気になるところです。
また、皆様にお願いですが、この記事については私の推測のもとで書いたことですので、この件に関して関係する鉄道事業社への問い合わせはご遠慮ください。